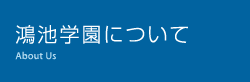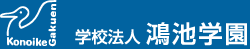昭和27年に幼稚園を始め、子供達に素晴らしい教育をと願い、ピアジェ理論にのめり込んでから、気がつけば半世紀以上が過ぎていました。
昭和27年に幼稚園を始め、子供達に素晴らしい教育をと願い、ピアジェ理論にのめり込んでから、気がつけば半世紀以上が過ぎていました。このページでは、ピアジェ博士の紹介と共に、私自身の思いを綴ることにしました。
私の大好きなピアジェ博士の言葉のひとつに、次の言葉があります。
「私自身探し求めている理想は、人生最後の日まで子供でいること。幼年期、それは最上の創造段階である。」
本当にその通りだと思います。 ピアジェ理論の素晴らしさを、皆様に少しでもお伝えできればと願います。
園長 松井 公男
ピアジェ博士について
J.ピアジェ博士
 『幼児の父』と呼ばれ、世界中から尊敬されている発達心理学の創始者J.ピアジェ博士をご存じですか・・・?
『幼児の父』と呼ばれ、世界中から尊敬されている発達心理学の創始者J.ピアジェ博士をご存じですか・・・?博士は60年以上にわたり多方面から人間の思考の発達について研究を行い、生物学、数学、論理学、哲学、発生学、認識論、心理学、教育学などの研究成果から、人間の思考がどのように発達するかを明らかにしました。
Learning is the process of developmental change.
Cognitive development is thinking development.
Thinking is Active Learning!
アメリカTIME誌掲載
 博士は世界で初めて0歳から7歳までの幼児の知能の発達を、臨床実験を幾度も重ね、科学的に解明しました。また哲学・心理学・生物学など、その他多くの分野でも影響を与えました。
博士は世界で初めて0歳から7歳までの幼児の知能の発達を、臨床実験を幾度も重ね、科学的に解明しました。また哲学・心理学・生物学など、その他多くの分野でも影響を与えました。1999年3月に発行されたアメリカTIME誌で、「20世紀に影響を与えた偉人100人」が選ばれましたが、その中でもさらに偉大な20人の中の一人として、アインシュタイン博士等とともにピアジェ博士の功績は讃えられています。
また、アインシュタイン博士は生前、ピアジェ博士の理論を評価して「難しい理論を最も単純に示す天才だ。」と言われました。
なぜ幼児教育は重要か
 ヨーロッパやアメリカの教育界でピアジェ理論が話題になるのは、0歳から7歳までの知能の発達をピアジェ博士が世界で初めて発表して以来、この理論を追い抜く理論が出てこないからです。
ヨーロッパやアメリカの教育界でピアジェ理論が話題になるのは、0歳から7歳までの知能の発達をピアジェ博士が世界で初めて発表して以来、この理論を追い抜く理論が出てこないからです。この知能の研究は、幼児教育者に「なぜ幼児教育は重要か」ということを科学的に証明してくれる根拠となるもので、勇気と希望を与えてくれる理論です。
ピアジェ理論をほんの一部、ご紹介致します。
ある日、1.4歳児の女の子が、博士の応接間に遊びに来て、窓をじっと見ていました。そこには蝶がとまって羽をひらひらしていました。見ていた女の子は手をひらひらさせ、蝶の模倣をし始めました。(直接模倣)
素晴らしい幼児の世界観
 ピアジェ博士はその他にも、幼児の世界観に素晴らしい知能が働いていることを明らかにしています。
ピアジェ博士はその他にも、幼児の世界観に素晴らしい知能が働いていることを明らかにしています。■1.
大人「お空に虹はどうしてできるの?」
幼児「こびとさんが絵の具で描くの。」
大人「そうか。でもこびとさんは虹の中には見えないよ?」
幼児「それは夜に描くから見えないの。」
大人「では、虹が消えるのはどうして?」
幼児「こびとさんがたくさん集まって、消しゴムで消すの。」
(人工論的実在性・アニミズム)
■2.
大人「片づけるってどんなこと?」
幼児「キンコンカンコンとチャイムが鳴ること。」
大人「どうしてそう思ったの?」
幼児「チャイムが鳴ると先生が片づけなさいと言うから。」
(結果論的)
■3.
大人「雨はどうして降るの?」
幼児「神様が鬼に命令して雨を降らせるの。」
(神秘論的)
幼児の夢と現実の狭間を行ったり来たりする世界は、幼児教育者や子育てをしているお母さんが見ることのできる世界であると同時に、ピアジェ理論を共有する世界です。
気づかないところで、博士の理論と関わっているのです。子供は大人の縮図ではなく、幼児独自の論理があることを博士は立証されたのです。
ピアジェ博士 年譜
 1896年 スイス ヌーシャテルに生まれる。
1896年 スイス ヌーシャテルに生まれる。7歳で自然科学に興味をもち、11歳の時にレマン湖に生息する白雀を観察した小論文が、博物館長のゴーデー博士に認められ、週二日学校が終わってから助手として手伝いながら、生物学を学ぶ。
15歳の時に、軟体動物(モノアラ貝)に関する小論文を発表する。この論文が大きな反響を呼び、多くの研究者から弟子にしてほしいと言われる。
■1915年
ヌーシャテル大学を卒業
■1918年
ヴァレ地方の軟体動物の研究で、博士号を取得。
チューリッヒ大学に入学。実験心理を学ぶ。
■1919年
フランス パリ大学に留学。
■1920年
ルソー研究所員となる。
■1929年
ジュネーブ大学理学部の科学思想史の教授、ルソー研究所副所長を務める。
■1939年
ジュネーブ大学社会学の教授。
■1952年
ソルボンヌ大学の教授。
■1955年
ジュネーブ大学に国際発生的認識論センターを創設。
■1970年
国際幼年教育者会議(主催:学園長 松井公男)の首席講師として日本へ初来日。
■1973年
ジュネーブ大学退官。
退官後も国際発生的認識論センターに通い、学際的研究に生涯をかける。
この共同研究は37巻以上。
博士はソルボンヌ大学を始め、ハーバード大学(1936年)、ケンブリッジ大学(1962年)、その他にも世界30ヵ国以上で名誉博士号を取得し、またユネスコスイス委員長やジュネーブ国際教育学会会長等、ジュネーブの光を遙か遠く彼方までもたらしました。
■1980年
逝去
■1996年
ジュネーブ大学主催 生誕100年祭、ヌーシャテル大学生誕100年祭、その他世界各国で生誕100年祭の式典が開催されました。
ピアジェ博士の生物学的実験 博士15歳
 ヨーロッパやアジアの湖に生息するモノアラ貝(軟体動物)は、通常は細長いのですが、スイスやスウェーデンに生息するモノアラ貝は、縮まって丸くなった変種です。
ヨーロッパやアジアの湖に生息するモノアラ貝(軟体動物)は、通常は細長いのですが、スイスやスウェーデンに生息するモノアラ貝は、縮まって丸くなった変種です。スイスの波の荒い湖水のモノアラ貝は、波に適応する為に凝縮(反射作用)の繰り返しによって丸く変形し、それが長年の間に遺伝されるものだ、という説に対し、博士は単なる習慣の固定ではなく、反射的レベルで環境と生態の間には相互的関係で結ばれており、単に環境からの受動的影響を受けるばかりではなく、生態そのものに主体的、能動的働きかけが一体として組み込まれているものだ、という説をとりました。
幼児教育にあてはめると、心的な初期段階では、環境と主体(幼児)は未分化の状態ですが、環境から受ける影響ばかりではなく、環境に対して働きかける(自分が今もっている知能で未知の世界に挑戦)能動的活動と、反省を繰り返し、心的体制を整えながら次の段階へと発達していくものであり、環境と個は相互に結ばれているという説をとりました。
このように、遺伝説を重視する傾向から、環境説との相互関係で教育を考え、一人一人の人間尊厳の教育に転換しなければならないことを示唆したのです。
ピアジェ博士 34歳頃 家族と共に
 左よりピアジェ夫人、長女ジャクリーヌ、次女リュシアン、
左よりピアジェ夫人、長女ジャクリーヌ、次女リュシアン、長男ローラン、ピアジェ博士
博士は天才的洞察力で三人の子供達を観察し、幼児の知能発達の研究を重ねていきました。
ピアジェ博士 74歳頃 研究室にて
 ピアジェ博士の研究室の机の上は、いつも素晴らしく散らかっていることで有名でした。
ピアジェ博士の研究室の机の上は、いつも素晴らしく散らかっていることで有名でした。しかし博士の頭の中では、何がどこに置かれているのかを全て把握していました。
(ピアジェ資料館)
ピアジェ博士 75歳頃 テンプル大学にて
 ピアジェ博士はアメリカのテンプル大学で名誉博士号を愛弟子のインヘルダー博士とともに授与されました。
ピアジェ博士はアメリカのテンプル大学で名誉博士号を愛弟子のインヘルダー博士とともに授与されました。(ピアジェ資料館)
ピアジェ博士 主な著書
 1920年 児童における判断と推理
1920年 児童における判断と推理1923年 児童における言語と思考
1926年 児童における世界表象
1927年 児童における物理的因果性
1932年 児童における道徳判断
1936年 児童における知能の誕生
1937年 児童における実在の構成
1941年 児童における量の発達
1942年 クラス・関係・数
1946年 児童における象徴の形成
児童における時間概念の発達
児童における運動概念と速度概念
1947年 知能の心理学
1948年 児童における空間表象
1949年 論理学概論
1950年 発生的認識論序説
1951年 児童における偶然観念の発生